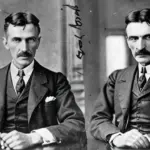新しい遺伝子編集の技術が、まるで押し寄せる潮のように世界に広がっている。
ニュースの見出しには「革命」という言葉が踊り、研究者たちは未来の医学を約束するかのように胸を張る。だが耳を澄ませば、その響きは案外古びた太鼓の音に似ている。――「病気は遺伝子を直せば治る」。
確かに、言葉の響きは単純でわかりやすい。小さな子どもでも理解できるだろう。壊れた部品を修理すれば機械が直るように、遺伝子を直せば人間も治る。そんな分かりやすさが、人々を惹きつけてやまないのだ。
けれども、現実はそう簡単ではない。遺伝子はただの部品ではなく、精妙な調和の上に成り立つ交響楽のようなものだ。ほんの一か所を切っただけでも、その響きは全体に波紋を広げ、思わぬ不協和音を生み出すかもしれない。誰もその先を完全に読み切ることはできない。そこに潜むのは、未知の危うさである。
それでも彼らは「一つの遺伝子が一つの病を生む」と説く。単一遺伝子疾患――嚢胞性線維症や鎌状赤血球貧血、テイ=サックス病などがそうだとされる。原因の遺伝子を突き止めたのだから、あとはそこを修正すれば病気は消える、というわけだ。
だが、もしそれが真実であるならば、すでにこの世には治癒例があふれているはずだ。ニュースのたびに「何千人が救われた」と報告されていて然るべきだ。けれど現実はどうか。せいぜい「一人の患者が改善した」といった小さな話があるだけで、病そのものが人類規模で消え去った例はどこにもない。
思い出されるのは、ワシントンD.C.の保健局が出した『Understanding Genetics』という書物の一節である。そこにはこうある。
「単一遺伝子疾患の多くは原因が明らかになってきたが、発症を防ぐ治療法も、進行を遅らせる治療法も存在しない」。
「多くの疾患にない」のか、それとも「すべてにない」のか。言葉は曖昧だが、現実を眺めれば後者に近いことがわかる。
結局、「単一遺伝子疾患」という響きのよさに比べれば、その証拠はまだ宙に浮いたままだ。興味深い仮説であり、研究を進める価値はあるだろう。だが、少なくとも現段階では未証明に過ぎない。
それでも研究者は、まるで魔法の呪文のように「原因は遺伝子」と唱え続ける。おそらく、そう言い切ることによって資金が集まり、人々の期待も高まるからだ。科学の世界もまた人間の営みである以上、名声や資金の力学から逃れることはできない。
その一方で、この「遺伝子万能説」は、別の可能性を覆い隠す役割も果たしている。病気の原因が環境にあるかもしれない――そうした視点を押しのけてしまうのだ。
大規模な企業活動による環境汚染、農薬や化学物質の影響、強力な薬やワクチンによる副作用。こうした因子に光が当たると、多くの責任が問われるだろう。だが「すべては遺伝子のせいだ」と言ってしまえば、企業も政府も安堵の息をつける。
遺伝子研究の聖杯はこうである。「環境の毒による害も、すべて遺伝子を直せば克服できる」。もしこれが実現すれば、企業は何をしても責められない。空気を汚そうと、川に化学物質を流そうと、「遺伝子治療があるから大丈夫」と言い張れる。人間の側を作り変えれば済むのだから。
だが、これはあまりに逆立ちした発想だろう。
私はこんな喩えを思い浮かべる。
もし雨が降るたびに猛毒が大地に降り注ぐとしたら。人が雨の中に立てば、当然苦しむ。普通なら「雨を止めよう」「毒をなくそう」と考えるはずだ。ところが研究者は言うのだ。「雨が悪いのではない。この人の体が悪いのだ。体を作り変えれば毒に耐えられる」。
こうして人間は改造を重ね、いずれ本来の姿を失っていく。どこかの時点で、それはもはや「人間」とは呼べない存在になるだろう。

これがトランスヒューマニズムの発想である。毒を退けるのではなく、人を毒に適応させる。たとえその過程で、人間が人間でなくなっても、それは「副作用」にすぎないと片づけられる。
やがて人は機械に置き換わり、毒にびくともしなくなる。「生き延びた」と称されるが、そこに生命はない。ただ調整された装置が稼働しているだけだ。それを「勝利」と呼ぶのである。
私はこれを誇張だとは思わない。UCLAで医学と技術、社会をつなぐプログラムを率いたグレゴリー・ストックは、かつてこう語った。
「たとえ世界の種の半分が失われても、多様性はなお残る。未来の人々は、この時代を自然が貧しくなった時代ではなく、新しい形態が次々と生まれた時代として記憶するだろう」と。
この言葉の背後には、「個人は重要ではない」という思想が横たわっている。半分の種が失われても構わない。多少の犠牲は未来の多様性に吸収される――そう考えるのである。
だが本当にそうだろうか。
私たち一人ひとりの存在は、取り換えのきく部品ではない。たとえ世界の多様性が保たれていても、ある個人の死や喪失は、他の誰かで埋められるものではないのだ。
健全な社会とは、本来「個人のために」存在するものである。社会のために個人が犠牲になるのではなく、個人を守り、支えるために社会がある。そこを取り違えたとき、科学も技術も、人間を傷つける刃へと変わってしまう。
――遺伝子研究の輝かしい未来を語るとき、私たちはその影も同時に見つめる必要がある。病を克服する希望を否定するつもりはない。だが、遺伝子だけに原因を押しつけ、環境や社会の責任を覆い隠すことは、やがて人間自身を空洞化させる。
遺伝子を直すのか。環境を直すのか。あるいは人間そのものを直してしまうのか。
選択の分岐点に立っているのは、技術者や研究者だけではない。私たち一人ひとりである。