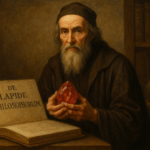日本人は古代中国の思想に対して、長いあいだ深い尊敬と親近感を抱いてきた。
孔子や老子をはじめとする賢人の思想は、千年以上の時を経てもなお、日本文化の骨格の中に生きている。
その中でも特に重要であり、同時に多くの誤解に包まれている命題が「性善説」と「性悪説」である。
日本人なら誰もが一度は耳にしたことがあるだろう。
しかし、「もう説明はいらない」と思った瞬間にこそ、理解は止まる。
むしろここにこそ、古代中国のインテリジェンス──知の深淵──が隠されている。
性善説と性悪説──単純な二項対立ではない
一般的な理解として、性善説は「人の本性は善である」とする孟子の思想、
性悪説は「人の本性は悪である」とする荀子の思想として知られている。
多くの人はこれを善と悪の対立構造として捉える。
つまり、「人はもともと善なのか、それとも悪なのか」という道徳的な問いとして理解してしまうのだ。
だが、そうした単純な構図で見る限り、この二つの思想の真意には到達できない。
実は孟子と荀子の関係は「対立」ではなく「連続」なのである。
時間軸のズレが意味すること
まず押さえておきたいのは、孟子と荀子が同時代人ではないという事実である。
両者の活動年代には、数十年の隔たりがある。
孟子の性善説が広く知られるようになってから、相当の時を経て荀子の性悪説が登場した。
このタイムラグが示すのは、荀子が孟子に反論するために性悪説を唱えたのではないということだ。
もし彼が単なる反対者ならば、孟子が存命中に直接論争を仕掛ければよかった。
そうではなく、荀子の性悪説は「孟子の思想を補うもう一つの視点」として提唱されたのである。
性悪説は性善説の補完である
孟子の性善説は、理想的な人間像を提示した。
「人の本性は善であり、正しく導かれなければ悪に傾く」。
つまり、教育と徳が人を善に保つ鍵であるという主張だ。
しかし、この命題には一つの論理的な欠落があった。
もし人の本性が善であるなら、なぜ悪は存在するのか?
なぜ人は誤り、他者を傷つけ、欲に溺れるのか?
荀子はそこに切り込んだ。
彼は人間の心を冷徹に観察し、「人の本性は悪である」と喝破した。
だが、これは人間への絶望ではない。
むしろ、「だからこそ教育と努力が必要だ」という現実主義的な補完だった。
つまり、性悪説は性善説の否定ではなく、
性善説を**現実に適用するための“対の理論”**だったのだ。
二つの命題は同じ結論に至る
性善説:「人の本性は善であり、正しく導かれなくては容易に悪に落ちる」
性悪説:「人の本性は悪であり、善とは人為によって形成された状態である」
一見、正反対のように見えるが、どちらの思想も導く結論は同じだ。
それは──
「正しい教えによって自らを律することが、君子となる道である」
孟子と荀子は、それぞれ異なる角度から同じ結論に到達している。
彼らは人間の二面性を補完し合う形で、一つの思想体系を完成させた。
日本人と良心──二つの思想の受け継ぎ方
日本では、孟子と荀子の思想は古くから儒教教育の根幹に組み込まれていた。
しかし日本的な受け止め方は、中国のそれとは少し違う。
日本人は「性善説」を信じつつ、「性悪説」も肌感覚で理解してきた民族である。
たとえば、「恥の文化」という言葉がある。
これはまさに性善説と性悪説の中間にある感覚だ。
人は本来善でありたいと願う(性善)、同時に悪へと傾く自分を恥じ、正そうとする(性悪)。
この二つの働きが、日本人の「良心」という独特の倫理観を形成している。
良心とは「自己監視の知」
性善説を知る者は、悪に誘惑されたとき、
自らの中の善性を思い出し、それに従おうとする。
性悪説を知る者は、自分の内に悪が潜むことを自覚し、
それを克服する努力を怠らない。
この二つの思考の往復運動こそが、良心のはたらきである。
つまり良心とは、外から与えられる倫理ではなく、
自らの内における「善と悪のせめぎ合いを観察する知」なのだ。
そして古代中国の知識人たちは、それを知性の核心──すなわちインテリジェンスと見なしていた。
対立ではなく調和──東洋的思考の深み
西洋哲学では「善と悪」「正と誤」はしばしば対立軸で語られる。
一方、東洋思想の特徴は相反するものの共存にある。
陰と陽、静と動、生と死──どちらも否定し合うのではなく、互いを映す鏡として存在する。
孟子と荀子の関係もその一例だ。
性善説と性悪説は、「人とは何か」という問いをめぐる両極でありながら、
その奥底ではひとつの循環する真理を形作っている。
子どもに「良心」を教える最もシンプルな方法
もしあなたが子どもに「良心とは何か?」と問われたとしよう。
そのとき、長い説教や道徳の話は必要ない。
ただ、孟子と荀子の二つの言葉を並べればいい。
「人の本性は善であり、正しく導かれなければ悪に落ちる」
「人の本性は悪であり、善とは努力によってつくられる」
この二つを合わせて考えるだけで、
“人が善を志す意味”を子どもでも直感的に理解できる。
そこには一切の装飾も回り道もない。
古代中国の思想家たちの「知」は、数千年を経てもなお、
教育の本質を貫いているのだ。
結語──古代中国インテリジェンスの深み
孟子と荀子の二つの命題は、
単なる倫理学ではなく、人間理解のインテリジェンス体系である。
彼らは善悪を論じることで、
「人がいかに自らを制御し、社会の秩序を保つか」という政治哲学を築いた。
そして日本人は、その思想を「良心」という形で受け継いできた。
悪に抵抗し、善を求め続ける意志。
そのせめぎ合いの中にこそ、人間の知性がある。
古代中国の思想を“インテリジェンス”と呼ぶのは、
単に知恵のことではない。
それは、人の内面に潜む光と闇を同時に見つめる知性のことなのだ。
性善説と性悪説──
このたった二つの言葉が、
人間という存在の深さを、これほど端的に言い表した例は他にない。
それこそが、古代中国インテリジェンスの底知れぬ深みであり、
私たちが今も学び続けるべき“思考の原型”なのである。