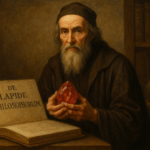序論:陰謀論の再定義
「陰謀論」という言葉は今日、軽蔑的に使われることが多い。
根拠のない憶測、社会不安を煽る言説、事実無根のデマ──そうした文脈で扱われるのが常である。
だが、近代史を俯瞰すれば、「かつて陰謀論とされたが、後に事実と確認された」ケースが存在することも否定できない。
その最たる例のひとつが、**モッキンバード作戦(Operation Mockingbird)**である。
1950年代から1970年代にかけて、CIAは国内外の主要報道機関に影響力を行使し、報道を国家戦略の一部として利用していた。
当初は冷戦下のプロパガンダ活動として正当化されたが、後にその実態は民主主義の根幹を揺るがす情報操作だったことが判明した。
この作戦は1975年のアメリカ上院「チャーチ委員会」(Church Committee)の調査により一部が暴露され、
今日では“陰謀論ではなく歴史的事実”として認識されている。
1. 背景──冷戦構造と情報戦の始まり
第二次世界大戦後、アメリカとソ連の対立は単なる軍事競争を超え、情報と認識の戦争へと発展した。
戦車やミサイルではなく、新聞・テレビ・ラジオを通じて「思想」を拡散し、敵国のイメージを形づくることが政治戦略の一部と化した。
CIAが設立された1947年以降、米国は国家安全保障法のもとで秘密工作を正当化し、
「自由主義陣営の防衛」という名目であらゆる心理戦を展開していった。
モッキンバード作戦は、こうした文脈の中で誕生した。
その目的は単純でありながら恐ろしく明快だった。
「報道を通じて、世界の世論を操作し、米国にとって都合の良い“現実”を形成すること」
2. 作戦の骨格──メディアと国家の接続線
モッキンバード作戦は、CIA広報部門の一部として極秘裏に運用された。
1950年代初頭、CIAは“文化的戦線(Cultural Front)”の名のもと、報道・芸術・教育を含む広範な分野でプロパガンダを展開していた。
この作戦では、アメリカ国内外の有力ジャーナリスト、報道機関の経営陣、通信社の編集幹部が密接に関与していた。
CIAは彼らを**協力者(assets)**と呼び、公式書類では「報告(reports)」という用語で記録している。
CIAの元職員によれば、この作戦に直接・間接的に関与したジャーナリストは少なくとも400人以上。
その中にはピューリッツァー賞受賞者も含まれており、活動範囲は情報収集から国際的な外交工作まで多岐にわたった。
ジャーナリストの中には、単に取材情報を提供するだけでなく、CIAの要請で記事を書き換えたり、
特定の出来事を報じないよう編集部に圧力をかける者もいたとされている。
3. 代表的事例:ジョセフ・アソップと報道スパイの実像
1953年、アメリカの著名なシンジケート・コラムニスト、**ジョセフ・アソップ(Joseph Alsop)**は、
表向きはフィリピンの選挙取材を名目に現地へ派遣された。
しかし、実際にはCIAの依頼による政治的工作活動に従事していたことが、後に公開された文書から明らかになっている。
アソップのケースは氷山の一角にすぎない。
当時、外国特派員や戦争記者の中には、情報提供者・外交仲介人・スパイとして活動する者が少なくなかった。
中でも紛争地帯で活動するフリーランス記者は、CIAからの報酬を受け取ることで生活を維持していたという。
報道の名を借りた諜報活動──
この構造がどれほど巧妙であったかは、CIAの元報道担当官が次のように述べている。
「最も効果的なスパイは、記者という仮面をかぶっている。なぜなら、彼らは“質問する権利”を持っているからだ。」
4. 協力メディアと組織的黙認
モッキンバード作戦の影響下にあったメディアとして、次の報道機関が挙げられる。
- アメリカ放送会社(ABC)
- ボイス・オブ・アメリカ(VOA)
- ユナイテッド・プレス・インターナショナル(UPI通信)
- ロイター通信
- ハースト・コミュニケーションズ、スクリプス・ハワード
- 『NEWSWEEK』誌
- 『ニューヨーク・タイムズ』
特にニューヨーク・タイムズの発行人アーサー・ヘイズ・スルツバーガーは、
CIAの協力者として名指しされており、情報収集や記事の選定に関与したとされる。
ここで注目すべきは、これらの協力が単に“個人の裏取引”ではなく、
企業として黙認されていた点である。
報道機関の経営陣は冷戦下の国家的立場を理解しており、
「自由主義陣営の防衛」という名目で協力を容認していた。
つまり、報道機関は単なる監視対象ではなく、国家の一部として機能していたのである。
5. 情報操作の技術──「報道しない自由」の誕生
CIAが用いた手法は、今日のフェイクニュースのように露骨な虚偽報道ではなかった。
むしろ、“報道しない自由”こそが最大の操作手段だった。
- 不都合な事実を報じない
- 別の話題を大きく取り上げて注意を逸らす
- 倫理・感情・正義の言葉を用いて世論を誘導する
これらは直接的な検閲ではなく、「編集方針」や「報道価値の判断」という名目で行われた。
ゆえに国民は操作されていることに気づきにくく、長期にわたる心理的効果を生んだ。
6. 作戦の縮小と潜在的継続
1973年、ワシントン・ポストの記者たちによる内部告発がきっかけで、
メディアとCIAの関係が公に批判されるようになった。
この圧力を受け、CIAは記者の直接雇用や指導を縮小したとされる。
しかし、それで終わりではなかった。
一部の記者は「スリーパー(潜伏工作員)」としてそのまま報道現場に残り、
必要な時期にのみ再び活動する仕組みが維持されたとされる。
1975年のチャーチ委員会報告書は、次のように結論づけている。
「CIAはメディアとの協力関係を構造的に形成しており、その範囲はアメリカ国内外を問わず、政治的影響力を及ぼすレベルに達していた。」
7. 現代的視点──SNS時代の「新モッキンバード」
モッキンバード作戦が終焉を迎えた半世紀後、情報の主戦場は紙と電波からアルゴリズムへと移行した。
かつてCIAが記者を操作していたように、いまや情報プラットフォーム自体が“編集者”となっている。
SNS上では、AIによる投稿検出・削除、トレンド操作、広告最適化などが日常的に行われており、
その背後には企業と政府のデータ共有協定が存在する。
この構造は、「国家とメディアの共謀」という旧来のモッキンバードを、
「国家とテクノロジー企業の共鳴構造」へと進化させたといえる。
つまり、モッキンバード作戦は終わったのではなく、デジタル空間に形を変えて継続している可能性がある。
8. 結論──情報の自由とは何か
モッキンバード作戦は、もはや陰謀論の領域ではなく、
「情報の政治的利用」に関する実証的な研究対象である。
この事件が示すのは、情報は単なる事実の伝達ではなく、力の行使であるという点だ。
情報を発信する者と受け取る者の間には、常に見えない非対称性が存在する。
その非対称性を意図的に拡大し、現実そのものを設計しようとしたのが、モッキンバード作戦だった。
そして現代においても、SNS・AI・アルゴリズムによって、
同様の情報支配構造が再び形を変えて現れている。
もはや問題は「真実がどこにあるか」ではなく、
「誰が“真実”という言葉を定義しているのか」である。
終章:歴史は繰り返す──だが形式を変えて
モッキンバード作戦は、報道の独立性を破壊した冷戦期の象徴として語られる。
だが同時に、それは現代社会への警鐘でもある。
フェイクニュースが溢れ、AIがニュースを生成し、SNSが世論を形成するいま、
我々は再び“見えない編集者”の手の中にいる。
情報の自由とは、情報が自由に流れることではない。
受け取る側が主体的に疑い、選び取ることができる状態を指す。
モッキンバードの教訓とは、
「権力が情報を支配する構造は常に再生産される」という厳しい現実であり、
その支配を見抜く力こそが、現代人に求められる新しいリテラシーである。
📚 参考文献・史料
- U.S. Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities (1975) “Church Committee Report.”
- Carl Bernstein, The CIA and the Media, Rolling Stone, 1977.
- Hugh Wilford, The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America (Harvard University Press, 2008).
- National Security Archive, Declassified CIA Records (2011–2020).